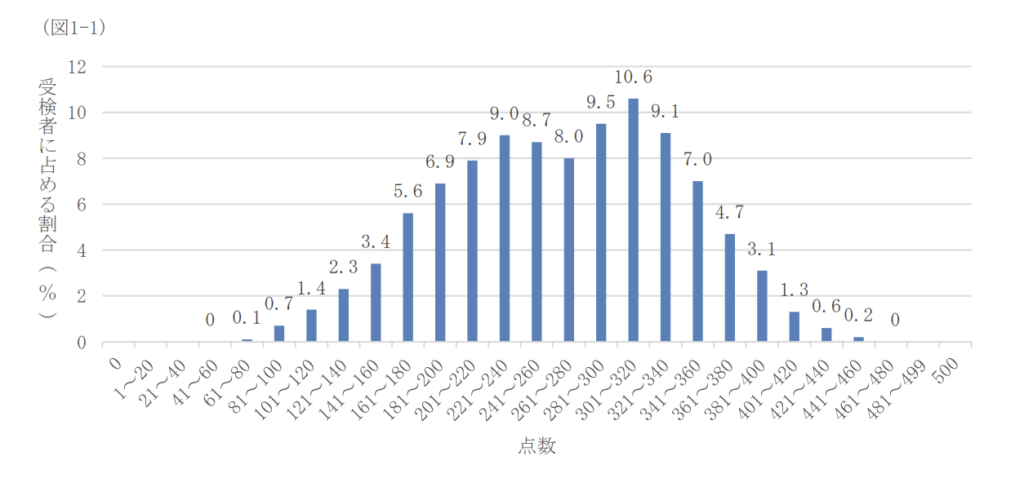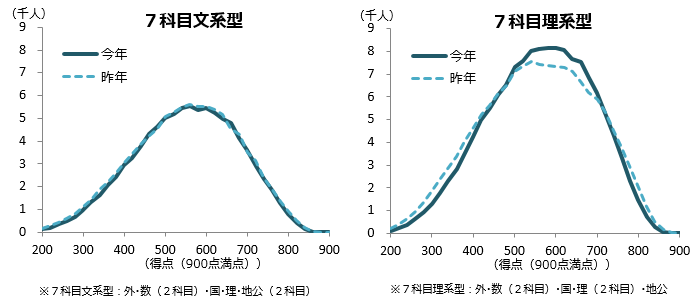※本記事の内容は、入試問題の出題傾向や思考過程を理解することを目的とした教育的分析に基づく再構成であり、実際の問題文・会話文・資料・図表・選択肢等をそのまま引用・転載したものではありません。
また、一部数式の表記が乱れています。
【時間 60 分】
────────────────────────────────
大問1 「強行遠足の今昔」:会話文+資料読解+数量処理+英作文
────────────────────────────────
次の【会話】は、甲府一高の「強行遠足」について、中学生向けの説明原稿を作る生徒たちと先生のやり取りである。
また【資料A】は、過去の「一高新聞」から抜粋した文章である。これらを読んで、後の問いに答えよ。
【会話】
生徒A「中学生に一高の魅力を伝えるなら、強行遠足は外せません。」
生徒B「でも昔の記事は言葉が難しいよね。説明原稿にするとき、言い換えが必要。」
先生「言葉の意味だけでなく、当時の背景も押さえよう。特に戦後直後は社会が大きく変わった時期だ。」
生徒C「最近の一高生は『意義』を『挑戦』とか『仲間との達成感』って言うけど、昔の記事は『合理性』とか書いてある。」
生徒D「合理性って、何が合理的なんだろう。運営? 体力? それとも精神面?」
先生「根拠になる記述を丁寧に拾い、条件に合う要約にまとめてみよう。」
【資料A(一高新聞より抜粋・表記は原文)】
…我らは極点を目指し、選手たり得る者のみが列に伍す。
遊山の徒は早々に退くべし。強行遠足は単なる苦行にあらず、
己の限界を知り、歩を整え、隊列を守り、全体の安全と進行を図るための合理なる訓練である…
(注)「極点」「選手たり得る」「遊山」は当時の言い回しである。
────────────────
設問1 表現の言い換え
────────────────
(1) 【資料A】中の「極点」を、中学生に伝わる分かりやすい表現に直せ。
(2) 【資料A】中の「選手たり得る」を、中学生に伝わる分かりやすい表現に直せ。
(3) 【資料A】中の「遊山」を、中学生に伝わる分かりやすい表現に直せ。
────────────────
設問2 資料からの推論:戦後の社会変化
────────────────
【資料B】
「昭和23年(1948年)の強行遠足の記録には、女子生徒の記述が見られない。」
(1) 昭和20年(1945年)以前に発生した出来事として適切なものを、次のア〜エから1つ選べ。
ア 日本国憲法の施行
イ 学制改革(6・3・3・4制の整備)
ウ 太平洋戦争の開戦
エ 女性参政権の実現(初の選挙)
(2) 昭和20年(1945年)から昭和25年(1950年)の間に起きた、日本の女性の政治的権利に関する大きな変化を簡潔に答えよ。
────────────────
設問3 「合理性」の比較:情報収集と要約
────────────────
あなたは「一高新聞」と直近10年間の一高生の意見を比較し、強行遠足の意義を説明する。
(1) 次のうち、比較のために収集する情報として最も適切でないものを1つ選べ。
ア 一高新聞の記述(合理性・訓練・安全に関する表現)
イ 直近10年間の生徒アンケート(意義・感想・改善点)
ウ 強行遠足当日の気温・降水などの気象記録
エ 生徒の好きなアニメ・ゲームのランキング
(2) 【資料A】の筆者が考える強行遠足の「合理性」を、次の条件をすべて満たして70〜90字でまとめよ。
【条件】①「安全」②「隊列」③「進行」④「訓練」の4語を必ず用いる。
(3) 次の【説明原稿(案)】を読んで、不十分な点の指摘として最も適切なものをア〜エから1つ選べ。
【説明原稿(案)】
「昔の一高新聞では、強行遠足は『合理的』だと書かれています。今の生徒も『達成感』があると言っています。だから昔も今も同じ意義があると言えます。」
ア 昔と今の意義を同一視しており、根拠となる記述の比較が不足している。
イ 文章が短すぎるので、必ず200字以上にする必要がある。
ウ 気温や降水を入れていないので、説明は不可能である。
エ 強行遠足の魅力は伝わるが、中学生向けではないので減点である。
────────────────
【設問4(差し替え用:追いつきが成立するデータ)】
【条件】
・Cさんは午前0時に出発し、一定の速さで歩く。
・DさんはCさんより遅れて出発し、一定の速さで歩く。
・休憩は考えない。
【記録(修正版)】
Cさん:午前2時に地点P(出発地点から $$12000$$ m)を通過し、午前5時に地点Q(出発地点から $$30000$$ m)を通過した。
Dさん:午前4時に地点P(出発地点から $$12000$$ m)を通過し、午前6時に地点Q(出発地点から $$30000$$ m)を通過した。
(1) Cさんの歩く速さ(m/分)を求めよ。
(2) DさんはCさんより何分遅れて出発したか求めよ。
(3) CさんがDさんに再び追いつく時刻(午前○時○分)を求めよ。
(4) (3)の再び追いつくまでの間で、CさんとDさんの距離が最大で何m離れたか求めよ。
────────────────
【設問5(補完:候補A〜Dの気温データ)】
次の表は、甲府・大泉・野辺山・佐久の気温(℃)の候補グラフA〜Dを、時刻ごとに数値化したものである。
各候補は「大泉」の推定が異なる。甲府・野辺山・佐久は共通である。
【共通(甲府)】 0時:6 1時:6 2時:5 3時:5 4時:6
【共通(野辺山)】 0時:-2 1時:-3 2時:-4 3時:-5 4時:-4
【共通(佐久)】 0時:1 1時:0 2時:-1 3時:-2 4時:-1
【候補A(大泉)】 0時:3 1時:2 2時:1 3時:0 4時:1
【候補B(大泉)】 0時:5 1時:5 2時:4 3時:4 4時:5
【候補C(大泉)】 0時:-1 1時:-2 2時:-3 3時:-4 4時:-3
【候補D(大泉)】 0時:2 1時:1 2時:0 3時:-1 4時:0
(1) 大泉の気温として最も適切なグラフ(候補A〜D)を選べ。
(2) 出発時の甲府(0時)と翌日3時の野辺山の気温差(℃)として最も適切なものを、次から選べ。
ア $$8$$ イ $$9$$ ウ $$10$$ エ $$11$$
(3) 午前3時の大泉と佐久の気温差(℃)を求めよ。
────────────────
設問6 英作文(55〜60語)
────────────────
【資料A】の内容に関連して、今までの人生の中で「他者と力を合わせて成し遂げた経験」を1つ述べる。
次の(ア)〜(ウ)の3点をすべて含み、55語〜60語の英語でまとめよ。
(ア) 成し遂げた経験の内容
(イ) 他者と協力しなければ成し遂げられなかった理由
(ウ) その経験を今後の高校生活にどのように活かしたいか
────────────────────────────────
大問2 山梨の森林:会話文+資料読解+理科・統計・英語
────────────────────────────────
次の【会話】は、山梨の森林について調べる生徒と先生のやり取りである。
また【資料C】は「森林資源の現状(令和4年度 山梨県林業統計書)」を参考に作成した抜粋、
【資料D】【資料E】は『森は海の恋人』『牡蠣の森と生きる「森は海の恋人」の30年』からの抜粋である。
これらを読んで、後の問いに答えよ。
【会話】
生徒E「山梨は森が多いけど、資源としてはどう評価されるんですか。」
先生「面積だけでなく、人工林の割合や齢級、林業の担い手なども見る必要がある。」
生徒F「海の豊かさにも森が関係するって聞きました。川が運ぶものが鍵なんですよね。」
【資料C(統計書より抜粋・要約)】
・県土に占める森林の割合:およそ $$78\%$$
・森林のうち人工林の割合:およそ $$45\%$$
・人工林の齢級は高齢化傾向がみられる。
・林業従事者数は長期的に減少傾向である。
【資料D(抜粋)】
森の土は雨を受け止め、腐葉土は水を蓄え、川へゆっくり流す。
川が運ぶ土砂や栄養は、やがて海の生き物を支える。
【資料E(抜粋)】
川がつくる三角州は、水と土が集まりやすく、作物の生育に適した条件がそろった。
人はそこを利用して暮らしを築いてきた。
────────────────
設問1 統計書から語句を探す
────────────────
会話文の( )に入る語句として適切なものを【資料C】から探し、答えよ。
生徒E「県土に占める森林の割合は約( )%なんですね。」
────────────────
設問2 資料読解:三角州・接続詞・腐葉土
────────────────
(1) 【資料E】の内容を踏まえ、川が運ぶ土砂でできた三角州が水田として利用された理由として適切なものを、次から1つ選べ。
ア 標高が高く冷涼で稲作に向くから
イ 水と細かい土が集まりやすく、平らな土地ができやすいから
ウ 海水が混ざるので病害虫が減るから
エ 森林が多いので用水が不要だから
(2) 【資料D】中の接続関係について、接続詞(または接続の役割)が「どの情報」と「どの情報」をつないでいるかを簡潔に説明せよ。
(3) 次の文の( )に入る語を、【資料D】中の語句を用いて答えよ。
「腐葉土は( )を蓄え、川へゆっくり流す役目をもつ。」
────────────────
設問3 5W1H分析→疑問の作り替え
────────────────
生徒は「豊かさ」について5W1Hで分析し、最初の疑問を作った。その後、調べ学習で分析をやり直し、疑問を作り変えた。
次の( )に入る内容として適切な文を入れ、完成させよ。
「豊かさを『経済の量』だけで測るのではなく、( )も含めて捉えると、山梨の森林の価値はどのように評価し直せるだろうか。」
────────────────
設問4 実地調査:場合の数・鳩ノ巣原理・箱ひげ図
────────────────
4人で渓流釣りに行き、地点a〜dの4地点で釣りをした。
(1) 4人全員が地点a〜dの異なる場所で釣りをする場合、場所の決め方は何通りあるか。
(2) 4人全員が12匹以上釣り、合計が52匹であった。このとき、同じ数の魚を釣った人が必ずいることを説明せよ。
【設問4(3)(補完:箱ひげ図データ+選択肢)】
2人の生徒XとYが釣った魚(各13匹)の全長(cm)を箱ひげ図にしたところ、五数要約は次の通りであった。
X:最小 $$12$$,第1四分位 $$15$$,中央値 $$18$$,第3四分位 $$20$$,最大 $$26$$
Y:最小 $$10$$,第1四分位 $$14$$,中央値 $$18$$,第3四分位 $$23$$,最大 $$24$$
次のうち、箱ひげ図から読み取れることとして正しいものを2つ選べ。
ア Xの方が中央値が大きい。
イ Yの方がばらつき(四分位範囲)が大きい。
ウ Xの方が最小値が小さい。
エ Xの方が最大値が大きい。
オ Xの方が全体の範囲(最大−最小)が大きい。
────────────────
設問5 水に溶ける元素:イオン・ろ過
────────────────
(1) 周期表の性質から、CaとClは陽イオンになりやすいか陰イオンになりやすいか、それぞれ答えよ。
【設問5(2)(補完:器具選択肢)】
ろ過に用いる器具として不適当なものを、次のア〜カから2つ選べ。
ア ろうと
イ ろ紙
ウ ビーカー
エ ガラス棒
オ 蒸発皿
カ 三脚
────────────────
設問6 英語:並べ替え+統合判断
────────────────
次の英文(ウェブサイト記事)を読んで、後の問いに答えよ。
(試験では下線部1と選択肢が提示される)
【設問6(1)(補完:下線部1の語群)】
次の語を並べ替えて、意味の通る英文を作れ。
( underline1 ) forests / nutrients / provide / that / support / life / in / rivers / and / the / sea
【設問6(2)(補完:英文選択肢)】
資料D・資料E・ウェブ記事の内容を組み合わせて考えたとき、最も適切な英文をア〜エから1つ選べ。
ア Forests only make rivers cleaner, but they do not affect the sea at all.
イ Forest soil and leaf litter help store water, and rivers carry nutrients that support life in the sea.
ウ Deltas are useless for farming because soil from rivers is always too poor.
エ The ocean becomes rich when people cut forests to increase sunlight on rivers.
────────────────────────────────
【ここまで】
────────────────────────────────